こんにちは。イシサムです。
資格試験に向けた勉強をする際、テキストを買ってみたものの、中々手につかず時間がだけが過ぎていく。
そんな経験はないでしょうか?私も資格に挑戦しているのですが、よくあります。
そんなとき、私は以下のステップで進めています。このステップで進めることで資格取得が以前より進めやすくなったと実感しています。
各ステップの紹介に移る前に、このステップを取り組む上で最も重要なポイントを挙げておきます。
それは「1度に完璧を目指さない」事です。以下でも触れますが、テキストを1周しただけで完ぺきに身につき、完璧にできるようになる人はいないと考えています。(少なくとも自分のような凡人には無理です)
スポーツや自転車の練習と同じで反復することで少しづつ、心と体で覚えていき記憶されることで、無意識でも可能になるのです。それが本当の意味での「身に付く」ということだと考えています。
そのようなポイントをふまえた上で、各ステップに触れていきます。
※資格についての考え方や取り組み方は過去の記事を参考に下さい。
最終期限を明確に決める
まず、ほとんどの人が「期限に向けてタスクを終わらせる」という行動を取ることを承知ください。
そのため、申込みをしない状態ではヤル気は起きにくいので、最終期限を決めるために資格の場合は申込みを、その他の事であれば仮でも良いので最終期限を決める(カレンダーにでも書いておくとよいです)ことが重要となります。
ざっくりとスケジュールを決める
最終期限を決めたら、自分が目指すゴールに対してどれくらいの量をこなす必要があるのか?を把握します。参考書やテキストであれば「◯章」といった形で章分けされている場合が多いと思うので、各章をどれくらいの時期に消化するか。を決めます。
最初に記載したとおり、1周で出来るようになることはないため、何周もする前提でスケジュールを組むと良いと思います。
やることを細切れにして、時間を決めて取り組む
ざっくりのスケジュールが決まったら、次に取り組む内容をさらに細かく区切ります。
例えば「1章」が50ページや50問あったとすると、数ページ〜10ページ以内に区切ります。
次に時間を決めて取り組みます。例えば10分以内で終わらせると決めて取り組みます。
問題集の場合は、本番を想定して区切ると更に効率的です。
例えば100問を100分のテストだとすると、10問を10分以内と決める。などです。本番に向けた時間感覚も同時に身につけられます。
最近あったのが、実際に解いてみると時間がかかる問題がありました。各問題の得点比率は同じ場合、そのような問題は一旦スキップして他の問題を先に解こう。といった作戦も考えられるようになります。(資格試験では、こういったケースは多いと思います)
そうすることで、締切効果が出て集中しやすい環境を作ることができます。
このとき、スマホなど自分が気が散る要因になるものは別の部屋においておくなどしておきましょう。せっかく集中し始めたのに通知などで逸れてしまうと、戻すのに大きなエネルギーと時間を要するためです。
この細切れにして時間を決めて取り組むというのは、ポモドーロ・テクニックと似た効果を得ることが出来ると考えているため、非常におすすめです。実際に私もこの方法を始めてから、問題集を消化する効率が格段に上がりました。
資格試験だけではなく、学生のテスト勉強や受験勉強、社会人のタスク消化にも効果があると思います。
慣れるまで違和感があると思いますので、まずは少量・短時間からチャレンジしてみると取り組みやすいです。
理解出来るまで繰り返す
1周目、2周目を行う中で、理解できてないと思った問題などをマークしておいて、マークしておいた問題だけ優先的に確認することで全体理解に対する効率が加速します。(私は都度正の字でつけるようにしています)
本番が近づいてきたらマークがついてないものも見ていくことで、実は理解の浅かった箇所についても漏れを防ぐことになります。
いかがだったでしょうか。どの資格においても最初は全然知らない状態からなので、1周目、2周目あたりはキツイのですが、それを超えると知識が身についた感覚が出てきて楽しくなってきますよ。
あくまで、私の体験ベースでの話なので皆さんにとって有益かはわかりませんが、参考にいただければと思います。
皆さんはどのような方法で取り組んでますでしょうか?

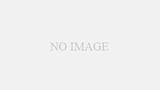
コメント